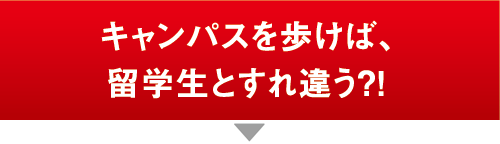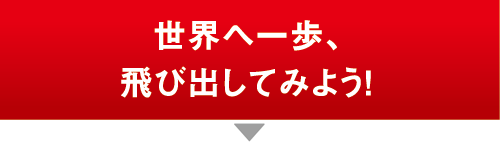毎日がグローバル。
日本に住むたくさんの外国人の、それぞれ異なる文化を知り、風習を認め合う。
それこそが、グローバル社会の一員になるスタートラインです。
名経大は、多国籍な留学生を4年間学ぶ学部生として積極的に招き入れています。
長期間ともに過ごすからこそ“グローバル”な環境が自然にあるのです。
キャンパスを歩けば、
留学生とすれ違う?!
14ヵ国459名の留学生が学ぶ大学

- ベトナム
- 215名

- 中国
- 146名

- ネパール
- 61名

- ウズベキスタン
- 13名

- インドネシア
- 5名

- 韓国
- 5名

- モンゴル
- 4名

- タイ
- 2名

- ナイジェリア
- 2名

- ミャンマー
- 2名

- スリランカ
- 1名

- 台湾
- 1名

- インド
- 1名

- パキスタン
- 1名
※2019年5月現在
留学生との国際交流イベント
グローバル人材プロジェクト
「企業見学及び日本文化体験」を実施

外国人留学生29人が参加。「美濃和紙」ものづくり体験、海外に事業を展開するエーザイ(株)とフェザー安全剃刀(株)の工場見学を行い、留学生たちは日本で就職するイメージを膨らませていました。
ハラール対応の
国際交流BBQパーティーを開催

外国人留学生と日本人学生の交流を目的として、バーベキューパーティーを開催。国籍や宗教を問わずみんなで楽しめるように、ウズベキスタンの学生有志が羊肉を中心としたハラール料理を準備しました。
インターナショナルウィーク「交流会」を開催
日本人学生、留学生など約160人が参加

テーマは「世界の料理を食べてみよう」。ウズベキスタン、スリランカ、タイ、パキスタン、中国、ネパール、ベトナムの7か国の留学生が約14種類の料理をつくり、あたたかな交流が生まれました。
外国人留学生含む28人が
天下の奇祭「石上げ祭」に参加

外国人留学生、日本人学生、教職員合わせて28人が、犬山市伝統の奇祭「石上げ祭」に参加しました。例年以上に学生たちの掛け声が大きく、国を超えて協力し合っていて、見事に登頂できました。
世界へ一歩、飛び出してみよう!


ここは世界に興味がある学生たちが集う場所! 多言語を話す教職員が、外国人留学生と日本人学生が交流するイベントを開催したり、慣れない生活にとまどう外国人留学生を支援したり、海外に興味を持つ日本人学生の相談に乗って海外研修や留学を取りまとめています。年々、外国人留学生が増えていることに伴って、さらに充実した内容に。どの経験も必ず将来の役に立つので、ぜひ気軽に足を運んでください。
まずは短期の海外経験から
カナダ、オーストラリア、イギリスなど、短期(2週間~数か月間)の語学研修を支援します。外国語を専門に学んでいなくても心配は要りません。多くの学生が、言語が異なっても気持ちが通じ合えることに喜びを感じ、自信をつけて帰国してきます。そして学業やキャンパス内での国際交流に積極的になったり、さらに長期留学に挑戦したりと大きく成長しています。あなたの興味や目的に合わせてホームステイ先やプログラムを紹介しますので、国際交流室の教職員に気軽に相談してください。
交換留学のチャンスが豊富に
新たに海外の3大学と交流提携協定を締結したため、教育や研究に関する交流がより盛んになります。今後もさらに増える予定です。交換留学はもちろん、海外でのインターンシップや編入学、大学院進学のチャンスも増え、より深みのある未来が広がります。
| 中華人民共和国 | 中国政法大学 法学分野で中国有数の教育を誇る大学。法律や中国事情などを中国語で学びます。 |
|---|---|
| ベトナム | ハノイ大学 NEW ベトナム有数の外国語大学。日本語学科の歴史はベトナムで最も長い大学の一つ。 |
| ホーチミン市法科大学 NEW 法律系学部を有する南部有数の大学の一つ。名古屋大学日本法教育研究センターあり。 |
|
| カナダ | ブリティッシュコロンビア大学 NEW 40にランクインするグローバルな総合研究大学。カナダ西部で最大規模。 |

今、旬な国へ!
ベトナム経済・社会研修プログラム
毎年多くの学生が参加する人気プログラムが、平成30年度海外留学支援制度(協定派遣・協定受入)プログラムに採択され、選抜者に奨学金が支給されるようになりました。プログラム内容は、本学の日本人学生とベトナム人留学生がともにベトナムへ渡り、留学生の実家でホームステイをするというユニークなもの。この体験は、これから日本とますます交流が深まるアジア新興国への興味につながります。
カナダ研修プログラム
2018年からスタートした新しい研修プログラムです。
事前にカナダの多文化についてフィールドワークやディスカッションを実施。3週間ホームステイをしながら、ブリティッシュコロンビア大学付属の語学学校(ELI)で学びました。帰国後は報告会を行い、各自でテーマ設定した課題の調査結果などを英語でプレゼンテーションしました。